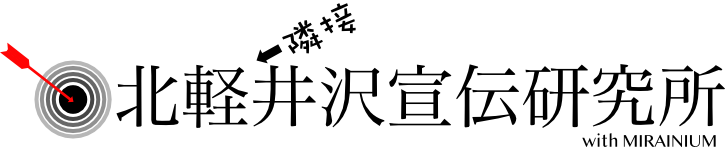問いが明確でなくては「書くぞ!」という意欲はなかなか湧いてきません。たとえば小論文の試験で「〜について述べよ」などと漠然としたテーマを与えられても何を書けばよいものやら途方にくれる人も多いはずです。何を書けばよいのかわからないのですから、当然ながら書くぞという気持ちのスイッチも入るはずがないでしょう。
書く気のスイッチを入れるには、たとえ与えられたテーマであってもそれを自分なりの問いに翻訳する作業が必要になってきます。それをいろいろな角度から眺め回すことで、そこに自分なりの切り口を発見するということです。そうしなければ、何を書くべきかが見えてこないし、それが見えてこない以上、「よし書くぞ!」というスイッチが入ることもないはずです。
スイッチが入るというのは、ある種の生体反応です。目の前にあるそれが、自分という存在をなんらかの形で脅かすものであると認識するからこそ人は、すわ一大事と重い腰を上げるのです。そして、これはなにも文章にかぎりません。おしなべて人の行動全般に共通するメカニズムでもあります。
人はなんらかの危機意識が生じなければ動きません。そして危機意識を生じさせるのは、じつは問いなのです。「なぜやるのか?」「なにをするのか?」「どうするのか?」といった問いです。それが明確に意識されてはじめて、その裏にある危機意識も浮かび上がってきます。その危機意識を認識することではじめてそれを解決しようという意欲が湧いてくるのです。
すなわち、問いというのはやる気を生み出す魔法のスイッチでもあるのです。